AI(人工知能)は、今や何を語る上でも外すことができないバズワードとして多くの人に認知されていますよね。最近では、スマートフォンやスマートスピーカーなど生活の中でも、数多くのAI(人工知能)が活用されていて以前よりも身近で、実用的な存在になりました。
AI(人工知能)の活用については、今後増々進んでいくことが予想されているだけでなく、現在では政府主導で社会への導入が推し進められているという側面さえあるほどです。
さて、このような社会的な流れがどのような背景をもとに作られているのでしょう。
それでは、AI(人工知能)導入が急がれる理由や、AI(人工知能)を活用しないことに対するリスクをいうものについてお伝えします。
AI(人工知能)を活用しないリスクと導入ニーズが高まり続ける理由


この数年のAI(人工知能)ブームは誰もが認めるところですよね。これまでもAI(人工知能)ブームは何回か巻き起こってきましたが、あくまでも「ブーム」として一過性のもので終わっていました。
ところが、現在高まっているAIの活用へのニーズは、一過性のブームではなく日増しに高まってきています。さらに、社会の様々な場面へのAI(人工知能)技術の導入と活用を政府主導で推し進められていて、今や私たちの生活に根付いた必須の技術と言えるでしょう。
このようなAI(人工知能)の活用に対する社会全体の意識や関心の変化は、なぜ起きているのでしょうか?その大きな理由のひとつが「少子高齢化」という「社会構造の変化」です。少子高齢化の深刻化への対策としてAI(人工知能)の活用が掲げられているのを耳にしたことはありますよね。では、なぜ少子高齢化への対策としてAI(人工知能)の活用が有効なのでしょうか。
少子高齢化とAI(人工知能)の活用を併せて考えることで、AI(人工知能)を活用しないことのリスクとAI(人工知能)導入を急務とすることの背景が見えてきます。
少子高齢化によるリスク1:人手不足


少子高齢化によるリスクと言って真っ先に挙げられるものは「人手不足」。高齢の方が増えて、生まれてくる子供が減る現象なので、結果として労働の担い手となる若い人手が足りなくなってしまいますよね。
この人手不足を補う1つの対策として期待を集めているものがAIの活用です。
これからの少子高齢社会にマッチした、AI(人工知能)を活用した自動業務を軸とした新しい組織体系や人材配置に取り組むことは、もはや避けることができない重要事項となっている現状で、AI(人工知能)の活用をしないことは大きなリスクとなっています。
少子高齢化によるリスク2:知識・技術の継承


少子高齢化によるリスクは、人材不足が「量的なリスク」だとすると、もう1つ「質的なリスク」として、「知識・技術の継承」という部分にも大きなリスクを抱えています。
このようなベテラン社員の放出に対して、その知識や技術の継承については間に合っていません。
こうした少子高齢化による質的なリスクに対しても、AI(人工知能)を活用することで対策することが急務になっています。ベテラン社員が持つ知識や技術をデータとして集約して、AI(人工知能)の技術を活用し、無人化することで、急速に進んでいくベテラン社員の定年後の穴埋めを機械的に補うことが重要となっています。
ベテラン社員の流出するスピードに対して、若手人材の成長スピードが追い付かない限りには、知識や技術が継承されずに流出していく一方なので、質的なリスクのほうが深刻ですよね。
少子高齢化にAI(人工知能)を活用しないことがクオリティ低下を招く
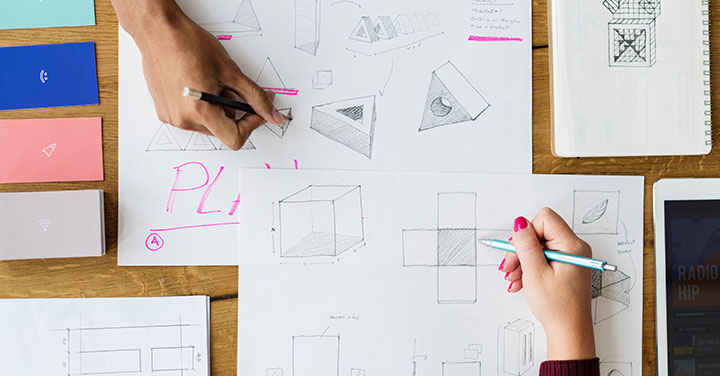
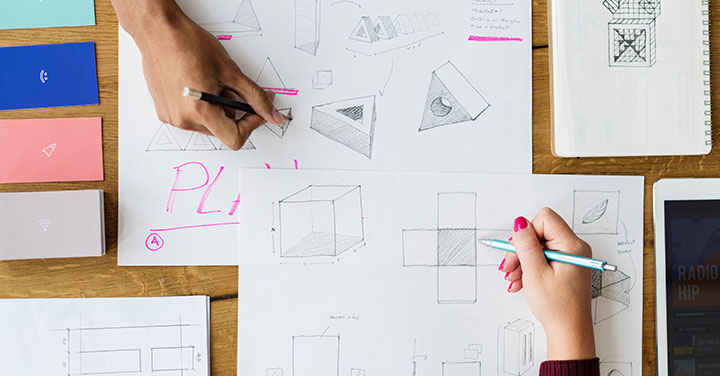
少子高齢化によるリスクとして、「人手不足」と「知識・技術の継承」という量と質に関する2つのリスクを見てきました。そして、この2つのリスクが引き起こす問題は「クオリティ低下」という品質に関する問題です。
少子高齢化は、このような品質維持に必要となる人材を奪い去ってしまいます。
現在、社会のなかで当たり前のように受けられるサービスなどを含めて、全ての「クオリティ」が低下してしまうと、とても大変なことになりますよね。電気や水道、ガスなど公共に関わるサービスを安定して利用することができなくなったり、食べ物や飲み物などを必要なときに手に入れることができなくなったりと、今の生活が一変してしまうでしょう。
このような「社会全体のクオリティ」を低下させないためには、少子高齢化の問題についてAI(人工知能)を活用した対策を早急に進めていくことが必須です。


少子高齢社会でのAI(人工知能)を活用しないリスクとAI(人工知能)導入を急ぐ背景についてお伝えしました。
少子高齢化を直接的に解決することは、現在の日本社会では難しい状況で、この流れを避けることはできません。そして、2025年には団塊の世代の人たちが全員75歳を迎える「超高齢社会」となり、少子高齢社会は進む一方です。
避けることができない少子高齢化に対応をするためには、AI(人工知能)を活用することで、少ない人手でも業務量をこなすために作業効率を改善することや、品質維持に必要となる知識や技術を継承することが喫緊の課題として求められています。
このような社会構造やニーズの変化が、これまでとは異なるAI(人工知能)の活用に対する重要度を高め、AI(人工知能)の導入を急がせているのでしょう。
現在は、少子高齢化への対策としてAI(人工知能)の活用が求められていて、今受けることができている社会サービスなどのクオリティ維持というのが目的となっていますが、これから先、もっとAI(人工知能)の活用が進みます。技術的にも進歩することで、これまで以上の生活クオリティをAI(人工知能)が実現してくれるというのが今後の理想ですよね!


