会社でプレゼンテーション資料作りは、とても時間がかかって面倒くさいものですよね。気がついたら、スライドの作成に多くの時間を取られてしまっている、といった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
さらに、通るかどうかも分からない企画のプレゼン資料を作ってプレゼンテーションを行うということは、メンタル面の強さも必要となり、時間だけでなく、あなたの持っている能力をフル活動させる必要があると言っても過言ではありません。
これだけ便利な時代になり、平成も終わろうとしている今でもなお、プレゼン資料作りは労働集約型の作業から脱却できていません。最新のパソコンやデバイスを使っていても、作業の仕方は言わば昭和の働き方です。
そんな悩みを抱える多くのビジネスマンをサポートすべく、AI(人工知能)がプレゼン資料を作ってくれるというニュースを入手いたしました。これからは、資料作成の最初から最後まで、最低限の作業をするだけで資料を作れてしまう時代が来るのです。
そこで今回は、AI(人工知能)がプレゼンテーションの資料作りで私たちの作業効率をグッと上げてくれる、そんなシーンについて解説いたします。これまでの古い働き方とは決別、今こそAI(人工知能)に新しい時代を切り開いてもらおうではありませんか。
![]()
![]()
プレゼン資料作成の工程
まず最初に、プレゼン資料を作った経験のない方でも分かるように、資料作成の工程についておさらいしておきましょう。とにかく、資料作成がどれだけ大変で時間がかかってめんどくさいのかについて、知ってもらい、
「これはさすがに人間業ではしんどいな、AI(人工知能)に資料を作ってもらわないとなぁ」と思ってもらう必要があります。
資料を作るために必要な作業は
- 資料のテーマ決め
- 内容の構成決め
- 材料の準備
- 実際の資料作成
と、ざっと並べてただけでもこれだけの工程があることが分かります。それでは、各工程について、どんな作業が必要かを見てみましょう。
1. 資料のテーマ決め
テーマとは、いわゆるプレゼンテーションの目的です。
つまり、
- 誰に対して
- 何をして欲しい
を決めるのです。これは、会社や上司から資料作成の指示を受けた時点で確認をする必要があり、もし上司から明確なテーマを伝えられなかったら、自分から「”誰に対して”、”何をしてもらう”ためのプレゼンテーション」かを確認することが必要です。
例として、役員向けの「新商品の企画」、営業本部長向けの「営業キャンペーンの実施」、顧客向けの「ITソリューションの提案」などです。このように、プレゼンテーションの対象となる人物を明確に定義しておくことが、この後の工程が考えやすくなりますので、必ず押さえておいてください。
2. 内容の構成決め
ここでは、1で決めたテーマを実現するために、どのような構成にするかについて考えます。
先ほど決めたテーマは、「誰かに何かをしてもらう」ということ目的ですが、逆に、「誰にも何もしてもらえなかった」らあなたのプレゼンは価値がないと判断されてしまいます。
せっかく多くの労力をかけて作成したプレゼンテーションの価値がゼロと言われるのは、あなたにとっても会社にとってもダメージは大きいものですので、できれば避けたいものです。そうならないためにも、ここではプレゼンの主たるメッセージについて、相手が魅力的に感じる具体的なメリットを考える必要があります。そのためには、あらかじめプレゼン対象の好みについてもリサーチする必要があります。
例えば、会社の経営者や上層部などは、数字やデータを重視する傾向があり、新商品の特徴や技術を説明するよりも、「20%のコストが削減」や「前年比30%増の売り上げが見込める」など、数字でメリットを訴えた方が、より相手に響くプレゼンになります。
3. 材料の準備
先ほど述べた”数字のメリット”を訴えるためには、それを裏付けるための情報が必要となります。例えば、
「20%のコスト削減」には、少なくとも2つの数値が必要です。
①今までのコスト
②今後のコスト(予測)
同様に、
「前年比30%増の売り上げが見込める」に必要な数値は、
①前年度までの売り上げ
②今後の売り上げ予測
となります。
つまり、過去の実績を鑑みて、今後の実績を予測していく推測の力が必要になるのです。実際にはこれらの数値の調査にはかなりの時間がかかる場合がありますが、プレゼンの成否はここにかかっているので、大いに力を注ぐ価値がある工程であることを覚えておいてください。
4. 実際の資料作成
これまでの工程で準備した材料を、下記のような流れに沿って並べます。
- 導入 課題と原因
- 本題 解決策と効果
- 結論 問題が解決できる
- 補足資料 データを裏付けするもの
先程までの工程で、プレゼン資料の材料はほぼ揃っているはずなので、全体のバランスを見ながら材料を並べる作業になります。プレゼン資料はストーリー性が重視されますので、この順番をしっかり守り、聞き手がスッキリするような流れにしてください。最後に、プレゼン資料の内容に矛盾点がないかを確認し、一旦プレゼン資料を完成させます。
次に、このプレゼン資料を使って実際のプレゼン行ってみましょう。他の人に見てもらい、スラスラとできているか、訴求力があるか、表情は適切かなどをチェックしてもらいましょう。
実際に、この資料でプレゼンテーションをしてみると、今まで見つけられなかった修正点を発見することができます。例えば、プレゼンをする上で資料の流れが不自然だったり、音読しにくい言葉が使われていたりすることがあり、このあたりを修正することで、自然な感じでプレゼンテーションをすることでき、アピール力も向上します。
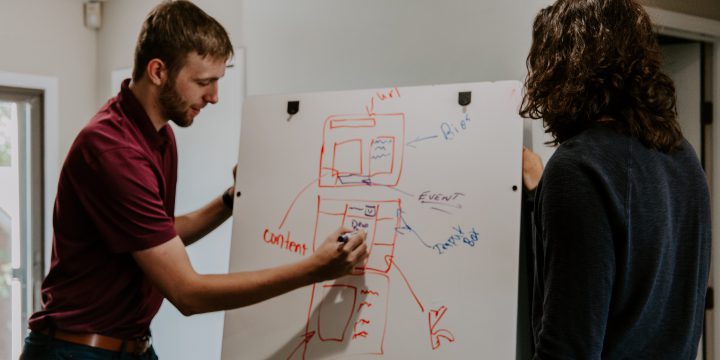
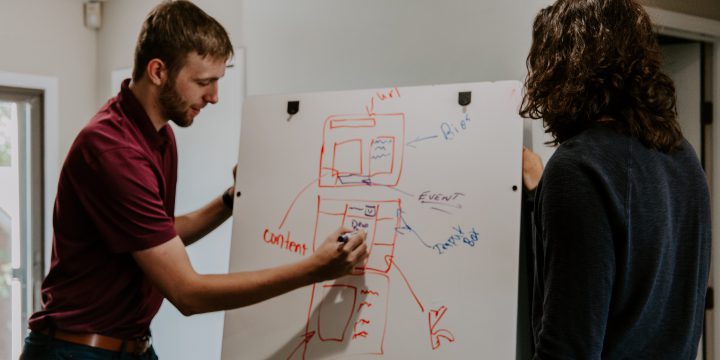
AI(人工知能)の資料作成の実力とは
いかがでしょうか、プレゼンの準備は、ここまでの多くの工程を経て準備をしているのです。平均的な話として、プレゼンテーションに準備する期間は5日と言われています。しかも、プレゼンは一回きりではなく、何度も何度も続くのです。時には同時に複数のプレゼンの準備をすることだってあり、プレゼンの準備は体力的精神的にかなりハードなものです。
こんな時こそ、AI(人工知能)に資料の準備をサポートしてもらう場面と言えます。実際に、AI(人工知能)がプレゼン資料の作成をサポートしてくれるWebサービスが登場し、無料のサービスも増えてきており、皆さんもお気軽に使うことができる環境が整いつつあります。これらのWebサービスではAI(人工知能)は資料の作成で次のようなサポートをしてくれます。
- 作成時間の短縮
AI(人工知能)の得意分野は何と言っても検索の速さで、資料に必要な情報を瞬時に検索してくれます。また、最近は画像検索が飛躍的に向上し、AI(人工知能)が資料に関連した画像も瞬時に検索してくれるのです。
これまでの検索の作業は、ほぼ手作業に近い形で検索をしており、かなりの時間を要してきましたが、その検索の大部分の時間を短縮することができます。ここ最近のAI(人工知能)の検索技術は格段に向上してきており、長い文章の要約ができるレベルにまで達しています。実際に、いくつかの新聞社でもこの技術利用されているほどです。 - 芸術的・効果的ビジュアルの資料を提案
ディープラーニングにより、AI(人工知能)は大量のプレゼン資料を学習し、プレゼンテーマに沿ったレイアウトや色などの提案をしてくれます。このAI(人工知能)が持っているプレゼン資料のパターンは1万を超え、ほとんどのジャンルをカバーできることが期待できます。


今回は、プレゼンを成功させるために、AI(人工知能)に資料を作らせると題して、AI(人工知能)の驚くべき実力について解説いたしました。
また、AI(人工知能)は資料の作成だけはなく、会議中にも活躍してくれます。例えば、リアルタイムで音声をテキスト化して擬似の作成をサポートし、そのテキスト化したキーワードを元に過去の資料を素早く引き出したり、プレゼン会議をトータルでサポートしてくれるのです。
これまでは、プレゼンの資料の作成に何日もかけてきましたが、AI(人工知能)がプレゼン資料をスピーディに作ってくれる時代がもうすでに始まっています。よって、大幅な時間短縮が実現すると、今まで全く縁のなかった働き方改革だって、あなたも体験することができる日が近づいてきているのです。ぜひ皆さんもAI(人工知能)の力を上手に使って、ワークライフバランスを充実させてください。
参照元 Beautiful.AI


